2019年01月24日
静岡県議会定例会一般質問
平成30年 静岡県議会定例会 一般質問(12月12日)
今年は「教育」を中心に子どもや学校現場、女性、障がい者が抱えている問題解決に向けての質問を行いました。

1 子どもたちを豊かに育むための環境づくりについて
(1)総合教育会議の今後の方向性について
質問内容
総合教育会議では、教育の現場で必要とされている施策の提言や、持続可能な未来のために教育で伝えなければならないことの示唆が期待されているが、総合教育会議の今後の方向性について知事の所見を伺う。
答弁内容(知事)
教育現場の状況を十分に考慮し、県教育委員会と意思疎通を図りながら、様々な課題の解決に向けた施策を具体的に実施することにより、地域ぐるみ・社会総がかりで、「ふじのくに」の未来を担う「有徳の人」づくりに取り組んでいく。
(2)教職員の多忙解消に向けて
質問内容
県が3年間かけて、教職員の長時間労働等の勤務環境改善に向けて取り組んできた「未来の学校『夢』プロジェクト」の成果と働き方改革を全県に普及するための方策について質問するとともに、スクール・サポート・スタッフ事業の拡充を要望する。
答弁内容(教育長)
市町と連携し、多忙化の解消に向け優れた事例の共有化を図り、公務の整理や外部人材の活用などを進める。スクール・サポート・スタッフについては国の事業を積極的に活用し、現場の要望に応じた配置に努める。
(3)外国籍児童生徒への教育充実について
質問内容
県内には多くの日本語指導が必要とされる外国人の子どもがいて、今後さらに増えることが予想される。学校では、言葉の壁だけでなく生活習慣や価値観の違いも超えて共に生活をしなければならない。一方で、外国人児童と学ぶことは、日本人の子どもにとっても多文化共生意識を育む有益なことである。外国人児童への教育をどのように推進していくのか伺う。
答弁内容(県教育長)
外国人の児童生徒の状況に応じた教育が十分に提供できるよう、市町と連携し保護者の勤務先企業の協力を得ながら、学校における更なる体制づくりを進める。
2 主要農作物種子法廃止への対応について
質問内容
稲、麦、大豆の種子安定提供を義務付けた種子法が廃止され、生産者・消費者からは不安の声が上がっている。県の農業を守り、主食の安心安全のためにどのような対応をしていくのか質問する。また、条約制定の必要性についても県の見解を伺う。
答弁内容(農林水産戦略監)
県は引き続き、種子生産として原種及び原原種の生産に取り組むこととし、関係市町や団体に対し採取事業を継続して実施する意思を通知したところである。条例の制定については、現状において万全を期しているものと考えているが、生産者や関係者に不安の声があるとすれば、条例制定の必要性の有無を検討する。
3 障がい者継続支援事業への支援について
質問内容
4月に障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬改定が行われたが、事業所の実態から離れたものとなっており、運営が困難になり閉鎖しなければならない事業所も出てきかねない。県は実態をどのように調査・把握し、課題に対する支援をしていくのか伺う。
答弁内容(副知事)
実態に即した運用を国へ要望することや事業所の自主製品の付加価値を高めるための支援を実施している。また、企業による発注拡大を強力に進める。障がいのある方が働き続け、経済的な安定はもとより、社会の一員として、生き生きとした生活が送れるように、共生社会の実現に努める。
4 性暴力被害者支援センターSОRAの機能充実について
質問内容
SORAの設立以来、想定を上回る相談が寄せられてきています。(4カ月で183件)今後、被害者の身体的ケアのためには病院との連携が必要だが、更なる拡充について県の考えを伺う。
答弁内容(くらし・環境部長)
ホームページに掲載するほか、全県高校、大学等の女子学生に案内カードを配布するなど周知に努めている。病院との連携について、心身への負担軽減のため、個別の待合スペースの確保などプライバシーへの配慮や相談員の同席による診察、緊急時における優先的な診療などの協力体制を構築している。
今年は「教育」を中心に子どもや学校現場、女性、障がい者が抱えている問題解決に向けての質問を行いました。
1 子どもたちを豊かに育むための環境づくりについて
(1)総合教育会議の今後の方向性について
質問内容
総合教育会議では、教育の現場で必要とされている施策の提言や、持続可能な未来のために教育で伝えなければならないことの示唆が期待されているが、総合教育会議の今後の方向性について知事の所見を伺う。
答弁内容(知事)
教育現場の状況を十分に考慮し、県教育委員会と意思疎通を図りながら、様々な課題の解決に向けた施策を具体的に実施することにより、地域ぐるみ・社会総がかりで、「ふじのくに」の未来を担う「有徳の人」づくりに取り組んでいく。
(2)教職員の多忙解消に向けて
質問内容
県が3年間かけて、教職員の長時間労働等の勤務環境改善に向けて取り組んできた「未来の学校『夢』プロジェクト」の成果と働き方改革を全県に普及するための方策について質問するとともに、スクール・サポート・スタッフ事業の拡充を要望する。
答弁内容(教育長)
市町と連携し、多忙化の解消に向け優れた事例の共有化を図り、公務の整理や外部人材の活用などを進める。スクール・サポート・スタッフについては国の事業を積極的に活用し、現場の要望に応じた配置に努める。
(3)外国籍児童生徒への教育充実について
質問内容
県内には多くの日本語指導が必要とされる外国人の子どもがいて、今後さらに増えることが予想される。学校では、言葉の壁だけでなく生活習慣や価値観の違いも超えて共に生活をしなければならない。一方で、外国人児童と学ぶことは、日本人の子どもにとっても多文化共生意識を育む有益なことである。外国人児童への教育をどのように推進していくのか伺う。
答弁内容(県教育長)
外国人の児童生徒の状況に応じた教育が十分に提供できるよう、市町と連携し保護者の勤務先企業の協力を得ながら、学校における更なる体制づくりを進める。
2 主要農作物種子法廃止への対応について
質問内容
稲、麦、大豆の種子安定提供を義務付けた種子法が廃止され、生産者・消費者からは不安の声が上がっている。県の農業を守り、主食の安心安全のためにどのような対応をしていくのか質問する。また、条約制定の必要性についても県の見解を伺う。
答弁内容(農林水産戦略監)
県は引き続き、種子生産として原種及び原原種の生産に取り組むこととし、関係市町や団体に対し採取事業を継続して実施する意思を通知したところである。条例の制定については、現状において万全を期しているものと考えているが、生産者や関係者に不安の声があるとすれば、条例制定の必要性の有無を検討する。
3 障がい者継続支援事業への支援について
質問内容
4月に障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬改定が行われたが、事業所の実態から離れたものとなっており、運営が困難になり閉鎖しなければならない事業所も出てきかねない。県は実態をどのように調査・把握し、課題に対する支援をしていくのか伺う。
答弁内容(副知事)
実態に即した運用を国へ要望することや事業所の自主製品の付加価値を高めるための支援を実施している。また、企業による発注拡大を強力に進める。障がいのある方が働き続け、経済的な安定はもとより、社会の一員として、生き生きとした生活が送れるように、共生社会の実現に努める。
4 性暴力被害者支援センターSОRAの機能充実について
質問内容
SORAの設立以来、想定を上回る相談が寄せられてきています。(4カ月で183件)今後、被害者の身体的ケアのためには病院との連携が必要だが、更なる拡充について県の考えを伺う。
答弁内容(くらし・環境部長)
ホームページに掲載するほか、全県高校、大学等の女子学生に案内カードを配布するなど周知に努めている。病院との連携について、心身への負担軽減のため、個別の待合スペースの確保などプライバシーへの配慮や相談員の同席による診察、緊急時における優先的な診療などの協力体制を構築している。
2017年04月09日
12月議会一般質問
~ 平成28年12月静岡県議会定例会 ~
質問者: 佐野 愛子 議員
質問日:2016/12/9 2番目
会派名:ふじのくに県民クラブ
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(1)障害者差別のないふじのくにづくり
答弁者 : 吉林副知事
質問要旨: 本年4月に障害者差別解消法が施行された。 県条例の制定の進捗状況と、障害のある方に対する差別の解消を推進し、誰にも優しいふじのくにの実現のために、どのような施策を展開していくのか伺う。
答弁内容:差別の解消を推進するための条例を制定し、全ての県民が一体となって障害に対する誤解や偏見を払拭し、障害を理由とする差別のない県民意識を醸成していく。公共交通機関など生活の場のバリアフリー化や、障害のある方に寄り添った配慮など、障害のある方々の視線を大切にした様々な備えをしっかり行い、全ての方々にとって優しく暮らしやすい“ふじのくに”となるよう取り組んでいく。
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(2)LGBTへの理解促進
答弁者 : 健康福祉部長
質問要旨: 性的マイノリティーの方々が、学校でも、職場でも、地域でも自分らしく生きていくことができるよう、まず県民の理解を深めることが必要と考える。今後どんな取組をしていくか伺う。
答弁内容: LGBTに関しての正しい説明や国の取組を、県人権啓発センターの機関紙に掲載するなど、広く県民に対して、理解を深め、偏見や差別が生じないように取り組んでいる。、教育現場や公務部署での一層の理解促進を図り、LGBTを含めた人権啓発活動に積極的に取り組み、全ての人の人権が尊重され、多様性を認め合うことができる社会を目指していく。
1 多様性のある県土 ダイバーシティーふじのくにの構築について
(3)企業のダイバーシティー経営の促進
答弁者 : 経済産業部長
質問要旨 性別、年齢、国籍、障害の有無、キャリア、ライフスタイルなどが異なる、多様な価値観を持った幅広い人材が多様化する顧客ニーズを的確にとらえ、新たな収益機会を取り込むための企画も生まれてくる。県が進めてきた、個々の雇用施策に加え、ダイバーシティー経営を県内企業で推進するべきと考える。県の所見を伺う。
答弁内容: 来年8月に策定する産業人材確保・育成プランでは、長時間労働の改善や、有給休暇の取得促進などの働き方改革を支援する施策を検討するとともに、ダイバーシティー経営の考え方も取り込み、女性や外国人、障害のある方などが自身の持つ能力を最大限に発揮し、誰もがいきいきと働くことができる社会の構築を目指していく。
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(4)若い女性に魅力ある県土づくり
答弁者 : くらし・環境部長
質問要旨: 県では「転出超過」が続いているが、将来子どもを産み育てる若い女性の確保が、人口増加の大きなポイントになっている。
経済や社会の活性化のため、今こそ、女性の視点や発想を取り入れるなど、女性の力が必要な時期に来ていると考える。
若い女性を静岡県に惹き付け、女性が輝く魅力ある県づくりについて、所見を伺う。
答弁内容: 「ふじのくに女性活躍応援会議」が中心となり県内で働く女性のネットワーク構築やロールモデルを増やし、多様な働き方を紹介し、女性自身の意識を高め、本県のイメージアップを図っていく。首都圏にはない静岡らしいライフスタイルの提案や、子育て環境の充実、まちの活気やにぎわいを創出することなどにより、本県の魅力の最大化を図り、静岡県で暮らしたいと多くの若い女性が望むように努める。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(1)静岡式35人学級の充実
答弁者 : 教育長
質問要旨: 来年4月からは、政令市へ定数給与に係る事務が移管され、定数決定権と税源もあわせて移譲されるが、行政的には分離しても、同じ静岡県としての目標は共有していくべきではないか。
移譲後の政令市は、これまで通り、少人数教育を推進していくのか。そして、県は移譲後の政令市とどのような連携体制を構築していくのか伺う。
答弁内容:静岡式35人学級編制を充実するために、25人の下限を撤廃し、36人以上学級の解消を検討している。静岡市、浜松市においても、少人数教育を充実するために、それぞれ必要な教員を配置する方向である。更に連携を強化し共通理解を図るとともに、静岡県の子供たちにとって、有益な教育環境の整備に努めていく。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(2)未来の学校「夢」プロジェクトの具現化促進
答弁者 : 教育長
質問要旨: 学校現場の多忙化解消には、教職員の意識改革など学校内の改善だけでは進まない。保護者や地域の方々に対して、本事業の理解・協力を得るためにどのような取組をしてくのか、また、人材をどのように活用して困窮を極める学校現場に対応していくのか、教育長に伺う。
答弁内容: 地域や保護者の方々はもちろんのこと、広く県民からも学校現場の多忙な実情と、この取組が教育活動の充実につながることを御理解いただけるよう、プロジェクトの成果を積極的に情報発信していく。スクールカウンセラーや学校支援サポーターなどの外部の専門スタッフの活用状況の分析を行い、教職員に加え地域人材も含めた「チーム学校」による指導体制を強化する。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(3)教員の資質向上のための新たな制度
答弁者 : 教育長
質問要旨: 教員育成協議会において現場の教職員の意向をしっかりと吸い上げる必要があると考える。
免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化が必要と考えるが、見通しをお聞かせいただきたい。
答弁内容: 教員育成協議会には、学校現場の課題や状況を教員育成指標に反映させるため、教育委員会や大学関係者や多様な教育関係者の参画についても検討していく。
中堅教諭等資質向上研修と免許状更新講習との整理・合理化については、10年経験者研修と免許状更新講習との重複感、あるいは負担感の解消のため、研修実施時期の弾力化等を今後も進めていく。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(4)「小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例」の実効ある取り組
み
答弁者 : 知事
質問要旨: この条例は、低迷する静岡茶の将来に明るい光をさしかけるものであると、県内の茶産業関係者が待ち望んでおり大きな期待をもっている。
小中学生がお茶を愛飲することによって、豊かな感性を育み生涯にわたってお茶を愛することを期待している。学校現場に負担なく、この条例が実効性をもち、県民全体の幸せにつながるための意気込みを伺う。
答弁内容: お茶の効能については、科学的・疫学的に健康効果が解明されている。この条例の制定によりお茶を飲む習慣がつくことで、子供たちが学校生活においてお茶を楽しみ、また、卒業してからも、後は成長してからも、長年にわたって健康維持・増進の効果を期待したいとしている。学校現場、市町及び茶業などの関係者、静岡茶の歴史・文化及び食育に関する有識者等からなる県民会議を設置する。学校現場に負担がないような提供を考慮する。
質問者: 佐野 愛子 議員
質問日:2016/12/9 2番目
会派名:ふじのくに県民クラブ
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(1)障害者差別のないふじのくにづくり
答弁者 : 吉林副知事
質問要旨: 本年4月に障害者差別解消法が施行された。 県条例の制定の進捗状況と、障害のある方に対する差別の解消を推進し、誰にも優しいふじのくにの実現のために、どのような施策を展開していくのか伺う。
答弁内容:差別の解消を推進するための条例を制定し、全ての県民が一体となって障害に対する誤解や偏見を払拭し、障害を理由とする差別のない県民意識を醸成していく。公共交通機関など生活の場のバリアフリー化や、障害のある方に寄り添った配慮など、障害のある方々の視線を大切にした様々な備えをしっかり行い、全ての方々にとって優しく暮らしやすい“ふじのくに”となるよう取り組んでいく。
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(2)LGBTへの理解促進
答弁者 : 健康福祉部長
質問要旨: 性的マイノリティーの方々が、学校でも、職場でも、地域でも自分らしく生きていくことができるよう、まず県民の理解を深めることが必要と考える。今後どんな取組をしていくか伺う。
答弁内容: LGBTに関しての正しい説明や国の取組を、県人権啓発センターの機関紙に掲載するなど、広く県民に対して、理解を深め、偏見や差別が生じないように取り組んでいる。、教育現場や公務部署での一層の理解促進を図り、LGBTを含めた人権啓発活動に積極的に取り組み、全ての人の人権が尊重され、多様性を認め合うことができる社会を目指していく。
1 多様性のある県土 ダイバーシティーふじのくにの構築について
(3)企業のダイバーシティー経営の促進
答弁者 : 経済産業部長
質問要旨 性別、年齢、国籍、障害の有無、キャリア、ライフスタイルなどが異なる、多様な価値観を持った幅広い人材が多様化する顧客ニーズを的確にとらえ、新たな収益機会を取り込むための企画も生まれてくる。県が進めてきた、個々の雇用施策に加え、ダイバーシティー経営を県内企業で推進するべきと考える。県の所見を伺う。
答弁内容: 来年8月に策定する産業人材確保・育成プランでは、長時間労働の改善や、有給休暇の取得促進などの働き方改革を支援する施策を検討するとともに、ダイバーシティー経営の考え方も取り込み、女性や外国人、障害のある方などが自身の持つ能力を最大限に発揮し、誰もがいきいきと働くことができる社会の構築を目指していく。
1 多様性のある県土ダイバーシティーふじのくにの構築について
(4)若い女性に魅力ある県土づくり
答弁者 : くらし・環境部長
質問要旨: 県では「転出超過」が続いているが、将来子どもを産み育てる若い女性の確保が、人口増加の大きなポイントになっている。
経済や社会の活性化のため、今こそ、女性の視点や発想を取り入れるなど、女性の力が必要な時期に来ていると考える。
若い女性を静岡県に惹き付け、女性が輝く魅力ある県づくりについて、所見を伺う。
答弁内容: 「ふじのくに女性活躍応援会議」が中心となり県内で働く女性のネットワーク構築やロールモデルを増やし、多様な働き方を紹介し、女性自身の意識を高め、本県のイメージアップを図っていく。首都圏にはない静岡らしいライフスタイルの提案や、子育て環境の充実、まちの活気やにぎわいを創出することなどにより、本県の魅力の最大化を図り、静岡県で暮らしたいと多くの若い女性が望むように努める。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(1)静岡式35人学級の充実
答弁者 : 教育長
質問要旨: 来年4月からは、政令市へ定数給与に係る事務が移管され、定数決定権と税源もあわせて移譲されるが、行政的には分離しても、同じ静岡県としての目標は共有していくべきではないか。
移譲後の政令市は、これまで通り、少人数教育を推進していくのか。そして、県は移譲後の政令市とどのような連携体制を構築していくのか伺う。
答弁内容:静岡式35人学級編制を充実するために、25人の下限を撤廃し、36人以上学級の解消を検討している。静岡市、浜松市においても、少人数教育を充実するために、それぞれ必要な教員を配置する方向である。更に連携を強化し共通理解を図るとともに、静岡県の子供たちにとって、有益な教育環境の整備に努めていく。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(2)未来の学校「夢」プロジェクトの具現化促進
答弁者 : 教育長
質問要旨: 学校現場の多忙化解消には、教職員の意識改革など学校内の改善だけでは進まない。保護者や地域の方々に対して、本事業の理解・協力を得るためにどのような取組をしてくのか、また、人材をどのように活用して困窮を極める学校現場に対応していくのか、教育長に伺う。
答弁内容: 地域や保護者の方々はもちろんのこと、広く県民からも学校現場の多忙な実情と、この取組が教育活動の充実につながることを御理解いただけるよう、プロジェクトの成果を積極的に情報発信していく。スクールカウンセラーや学校支援サポーターなどの外部の専門スタッフの活用状況の分析を行い、教職員に加え地域人材も含めた「チーム学校」による指導体制を強化する。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(3)教員の資質向上のための新たな制度
答弁者 : 教育長
質問要旨: 教員育成協議会において現場の教職員の意向をしっかりと吸い上げる必要があると考える。
免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化が必要と考えるが、見通しをお聞かせいただきたい。
答弁内容: 教員育成協議会には、学校現場の課題や状況を教員育成指標に反映させるため、教育委員会や大学関係者や多様な教育関係者の参画についても検討していく。
中堅教諭等資質向上研修と免許状更新講習との整理・合理化については、10年経験者研修と免許状更新講習との重複感、あるいは負担感の解消のため、研修実施時期の弾力化等を今後も進めていく。
2 子供たちを豊かに育むための環境づくりについて
(4)「小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例」の実効ある取り組
み
答弁者 : 知事
質問要旨: この条例は、低迷する静岡茶の将来に明るい光をさしかけるものであると、県内の茶産業関係者が待ち望んでおり大きな期待をもっている。
小中学生がお茶を愛飲することによって、豊かな感性を育み生涯にわたってお茶を愛することを期待している。学校現場に負担なく、この条例が実効性をもち、県民全体の幸せにつながるための意気込みを伺う。
答弁内容: お茶の効能については、科学的・疫学的に健康効果が解明されている。この条例の制定によりお茶を飲む習慣がつくことで、子供たちが学校生活においてお茶を楽しみ、また、卒業してからも、後は成長してからも、長年にわたって健康維持・増進の効果を期待したいとしている。学校現場、市町及び茶業などの関係者、静岡茶の歴史・文化及び食育に関する有識者等からなる県民会議を設置する。学校現場に負担がないような提供を考慮する。
2015年02月12日
佐野愛子代表質問に立つ
静岡県議会の平成27年2月定例会 本会議初日(2月18日)に、ふじのくに県議団の代表として、佐野愛子県議が質問いたします。教育界の代表として、働くものの代表として、女性の代表として、下記の質問を行い、県政に愛の風を吹かせます。
議会の様子は、静岡県公式ホームページ(http://www.gikai-chuukei1.pref.shizuoka.jp/)にて生中継や録画中継を行っております。後援会主催の議会傍聴に参加いただけなかった方は、ぜひご覧ください。
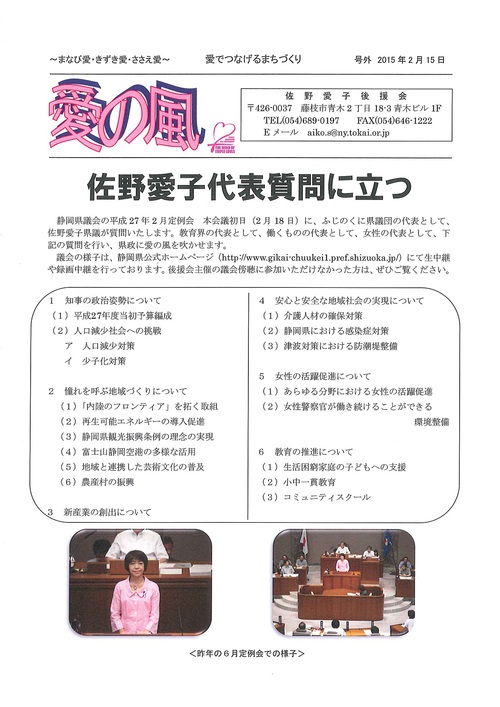
議会の様子は、静岡県公式ホームページ(http://www.gikai-chuukei1.pref.shizuoka.jp/)にて生中継や録画中継を行っております。後援会主催の議会傍聴に参加いただけなかった方は、ぜひご覧ください。
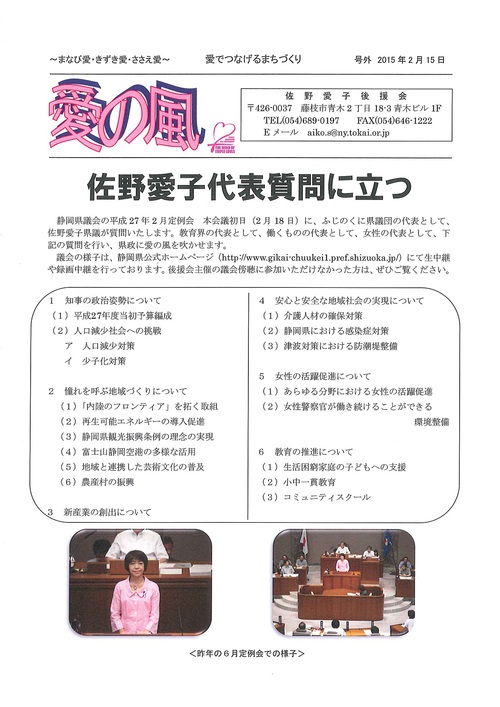
2015年01月10日
三つの愛と平和
三つの愛と平和
静岡県議会議員 佐野愛子
三つの愛は「まなび愛」、ここから始まります。
「理想のふじのくに」に生まれたすべての子どもたちが、
生き生きと育つように全力で取り組みます。
「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」
の気持ちを学び、「きずき愛」「ささえ愛」に取り組む
ことが、本来の豊かな生活づくりや安心・安全な暮らし
づくりにつながると確信しています。
三つの愛が力強く成長して、波紋のように広がり、
平和の礎となることを目指して活動していきます。
静岡県議会議員 佐野愛子
三つの愛は「まなび愛」、ここから始まります。
「理想のふじのくに」に生まれたすべての子どもたちが、
生き生きと育つように全力で取り組みます。
「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」
の気持ちを学び、「きずき愛」「ささえ愛」に取り組む
ことが、本来の豊かな生活づくりや安心・安全な暮らし
づくりにつながると確信しています。
三つの愛が力強く成長して、波紋のように広がり、
平和の礎となることを目指して活動していきます。
2015年01月10日
2014年09月17日
静岡県の学力問題について
静岡県の学力問題について
1 公表について
9月4日、県のHPに全国学力テストの小学校の4科目の県内市町の平均正答率と、国語Aの平均点以上だった校長名262人があいうえお順にずらっと公表されました。
昨年来、県内の各学校でテスト対策、授業改善に力を入れて行った結果、今年度は大幅な改善が見られて安堵していたところではありますが、校長名の公表は的外れと言わざるを得ません。例えば今年度4月に赴任してきた校長はテストを実施するまでのたった2週間で成果を出したというのでしょうか。教員の間では人事異動の運が良かったとしか認識していません。学校はあくまでもチームプレー、教職員全体での連携した成果です。「子どもの学力は教師の責任」という理由での校長名公表でありますが、一人の先生の力だけでなんとかなるものではありません。地域や家庭環境などが大きくかかわってきます。校長にしても学級担任にしても名前が挙がって褒められるために日々指導しているのではありません。
また、公表に関しては市町村の同意を得るという文科省の実施要項に違反することを承知で、公表しています。平均正答率等を一覧表にすることも認められていません。「昨年度、規則を無視しても公表したことにより今年の成果が出た。」かもしれませんが、成果を出すためには規則を守らなくてもいいのでしょうか。第一に子どもたちに対して規範意識を育てようとしているときに、知事が率先して規則破りをしていることは示しがつきません。市町の教育委員会が慎重に公表の方法を検討していることを飛び越えてしまったことも県として示しがつきません。
学力テスト実施要領の中に知事が公表してはならないという文言はないかもしれません。それは、そもそも知事が介入してくるという前提はないからです。教育委員会あてに作成している規則なので知事の権限は及ばないはずです。
昨年度の6年生(現在の中学1年生)は、全国最下位と騒がれて、「自分たちはダメな学年なんだ。」と劣等感を抱いてしまっていることが心配です。そして、今年の6年生が挽回したとなるとますます立場が悪くなります。子どもたちの自信を失わせる結果となったのでは意味ありません。
2 平均点というもの
数字で表されるのはあくまでも平均点です。平均点とは周知のとおり全員を対象としています。特別支援を必要とする子、外国籍の子どもがクラスにいれば当然平均点は下がります。今、「共生」の教育の理念の下、障害のある子もない子も、国籍が違っても地域で助け合いながら学ぼうということに重点が置かれています。義務教育は地域のどんな子もすべて受け入れる場です。塾や高校とは違うのです。すべての子に等しい学力を身に着けさせるという理想に向かって日々奮闘しているのです。保健室登校の子にも「名前だけでも書いてごらん。」「できるところだけでいいから答えてごらん。参加することに意義があるんだよ。」と認め励ましています。「平均点」ばかり重視すると子どもたちの間にも「あの子はできない子、平均点を下げる子」という暗黙の差別が起こりいじめにつながりかねません。
現に特別支援を必要とする子どもの保護者から、「これからこの学校に置いてもらえるか心配。」という声や外国籍の子どもも「テストできなかった。」と心配している声が届いています。
教室では、一人ひとりの伸びを認め合っています。できないことががんばってできるようになったことが大事なのです。はじめから90点を取る実力がある子が95点をとることよりも、これまで20点だった子が30点になったことのほうが価値あるのかもしれません。平均ではなくてあくまでも「個」なのです。
3 本当の学力と生きる力
「教室は間違うところだ。」
学級目標として教室の前面に掲げてあるクラスがあります。
「えっ、間違えちゃ困る、ちゃんと正答を覚えるところが教室じゃないか。」と思われる方も多いでしょう。
しかし、静岡県の教職員には全く違和感がない目標です。教員は絶えず子どもたちに
「間違ってもいいんだよ、思い切って自分の考えを言ってごらん。」
「間違ったことを言った子を笑ったりしたらいけないよ。間違った意見があるからでみんなが考えてしっかり覚えることができるんだよ。」と語りかけています。
「学び方を学ぶ」ことが、義務教育を通じてつけたい力です。答えは一つでもたくさんの違った考え方があること、その考え方の筋道を表現しあい共有しあうことに集団学習のだいご味があります。
実験を通して、また理科園や畑で体験活動を通して子どもたちは気づき学びを広げていきます。そんなときの子どもたちは生き生きと目を輝かせて新しいことを発見し知識を積み重ねていく楽しさを体感するのです。
苦手なことや難しいことにも意欲を持ってチャレンジしようとする心、できなくても先生や友だちに励まされて頑張って克服していく態度、義務教育は人生の基礎を作る場です。
大人のみなさん、現在は厳しい競争社会に身を費やし勝ち抜くことが大事なことはわかります。
しかし、そんなみなさんも小学生の時のことを思い出してみてください。先生に怒られたこと、褒められたこと、友だちと遊んだことなどなど、どんなことが思い出されますか?
今社会で頑張れている基礎は、義務教育の時に先生から
「00ちゃんはやればできるじゃん。」「00ちゃんは絵がうまいね。いいとこあるね。」「すごいすごい、がんばったね。」
などと励まされ認められたから今があるのではないですか?
また、もしかしたら悪いことをした自分を泣いてしまうほど厳しく叱ってくれた経験かもしれません。
とにかく、義務教育は競争至上主義ではないことだけは確かです。
4 小学校国語Aの持つ意味
昨年の「全国学力・学習状況調査」で、小学校国語A問題が全国47位、最下位という結果に全県民が衝撃を受けました。しかしそれが、「静岡県の子どもの学力は全国最下位」というように過大解釈されたように思います。さらに「静岡県の学力は危機的状況。」「静岡県の授業は最低。」などという発言まで飛び出しました。
よく考えてみてください。義務教育9か年あるうちの、小学校6年生。そして国語Aと国語B、算数Aと算数Bがある中で、国語Aだけが最下位だったわけです。それが、「静岡県のすべての学力」のようになってしまいました。
同じ年に実施した中学校3年生は総合得点では全国6位です。これが評価されないで小学校の国語A最下位だけが大きく独り歩きしてしまいました。
それからというもの、新聞では「静岡県の学力」という特集が一年を通じて組まれ全県民が危機感をあおられました。使っている副教材が悪いからだという指摘も出ました。県議会本会議でも文教常任委員会でも質問の中心的話題になりつづけました。
しかし、またよく考えてみると、それほど県民こぞって県政こぞって問題視する重大な課題だっだのでしょうか?
静岡県の人口流出、北海道に続き全国ワースト2、企業立地数毎年減少などもっと重大な課題はあると思うのですが。
確かに騒いでくれたおかげで授業の見直しやテスト対策が進み、今年の結果は大幅に向上しました。
しかし、学校のことは学校を信用して任せてくれればなんとかします。
5 今後のありかた
全国学力調査の実施には60億円もの予算が使われています。日本全国、地域の学力を調査する目的のためなら、全校実施する必要はなく抽出方式で5%ほどのデータを採取すれば十分なはずです。
また、静岡県では国から結果が返ってくる前に、各学校で教師が採点をしておよその結果をつかんでいます。つまり、国ではベネッセなど外部委託して採点分析をし、県内すべての学校でも全員の分の解答用紙をコピーしてから採点し分析をするという二重の手間をかけているのです。結果を早くつかんで対応し指導するためということですが果たしてそれだけの費用対効果があるのか疑問です。
「私は、静岡の教育を受けて育った。」と県民が胸を張って語ることができるように、また教職員も「静岡の教育は真の教育だ。」と自信を持って教壇に立つようにしていかなければなりません。現に、全国の教育研究集会では、静岡県の実践発表は質が高い上に絶えず新しい取り組みを続けていることで高い評価を受けています。
全国テストの問題傾向が今の日本につけたい力であることは確かなので、授業改善に取り入れていくことは必要です。しかし、これまでに述べたように点数主義、競争主義に陥ることなく、目の前の子どもたちに「学ぶ力」をつけさせるという大事な目標に向かって心を一つにしていくことが何より大事です。
1 公表について
9月4日、県のHPに全国学力テストの小学校の4科目の県内市町の平均正答率と、国語Aの平均点以上だった校長名262人があいうえお順にずらっと公表されました。
昨年来、県内の各学校でテスト対策、授業改善に力を入れて行った結果、今年度は大幅な改善が見られて安堵していたところではありますが、校長名の公表は的外れと言わざるを得ません。例えば今年度4月に赴任してきた校長はテストを実施するまでのたった2週間で成果を出したというのでしょうか。教員の間では人事異動の運が良かったとしか認識していません。学校はあくまでもチームプレー、教職員全体での連携した成果です。「子どもの学力は教師の責任」という理由での校長名公表でありますが、一人の先生の力だけでなんとかなるものではありません。地域や家庭環境などが大きくかかわってきます。校長にしても学級担任にしても名前が挙がって褒められるために日々指導しているのではありません。
また、公表に関しては市町村の同意を得るという文科省の実施要項に違反することを承知で、公表しています。平均正答率等を一覧表にすることも認められていません。「昨年度、規則を無視しても公表したことにより今年の成果が出た。」かもしれませんが、成果を出すためには規則を守らなくてもいいのでしょうか。第一に子どもたちに対して規範意識を育てようとしているときに、知事が率先して規則破りをしていることは示しがつきません。市町の教育委員会が慎重に公表の方法を検討していることを飛び越えてしまったことも県として示しがつきません。
学力テスト実施要領の中に知事が公表してはならないという文言はないかもしれません。それは、そもそも知事が介入してくるという前提はないからです。教育委員会あてに作成している規則なので知事の権限は及ばないはずです。
昨年度の6年生(現在の中学1年生)は、全国最下位と騒がれて、「自分たちはダメな学年なんだ。」と劣等感を抱いてしまっていることが心配です。そして、今年の6年生が挽回したとなるとますます立場が悪くなります。子どもたちの自信を失わせる結果となったのでは意味ありません。
2 平均点というもの
数字で表されるのはあくまでも平均点です。平均点とは周知のとおり全員を対象としています。特別支援を必要とする子、外国籍の子どもがクラスにいれば当然平均点は下がります。今、「共生」の教育の理念の下、障害のある子もない子も、国籍が違っても地域で助け合いながら学ぼうということに重点が置かれています。義務教育は地域のどんな子もすべて受け入れる場です。塾や高校とは違うのです。すべての子に等しい学力を身に着けさせるという理想に向かって日々奮闘しているのです。保健室登校の子にも「名前だけでも書いてごらん。」「できるところだけでいいから答えてごらん。参加することに意義があるんだよ。」と認め励ましています。「平均点」ばかり重視すると子どもたちの間にも「あの子はできない子、平均点を下げる子」という暗黙の差別が起こりいじめにつながりかねません。
現に特別支援を必要とする子どもの保護者から、「これからこの学校に置いてもらえるか心配。」という声や外国籍の子どもも「テストできなかった。」と心配している声が届いています。
教室では、一人ひとりの伸びを認め合っています。できないことががんばってできるようになったことが大事なのです。はじめから90点を取る実力がある子が95点をとることよりも、これまで20点だった子が30点になったことのほうが価値あるのかもしれません。平均ではなくてあくまでも「個」なのです。
3 本当の学力と生きる力
「教室は間違うところだ。」
学級目標として教室の前面に掲げてあるクラスがあります。
「えっ、間違えちゃ困る、ちゃんと正答を覚えるところが教室じゃないか。」と思われる方も多いでしょう。
しかし、静岡県の教職員には全く違和感がない目標です。教員は絶えず子どもたちに
「間違ってもいいんだよ、思い切って自分の考えを言ってごらん。」
「間違ったことを言った子を笑ったりしたらいけないよ。間違った意見があるからでみんなが考えてしっかり覚えることができるんだよ。」と語りかけています。
「学び方を学ぶ」ことが、義務教育を通じてつけたい力です。答えは一つでもたくさんの違った考え方があること、その考え方の筋道を表現しあい共有しあうことに集団学習のだいご味があります。
実験を通して、また理科園や畑で体験活動を通して子どもたちは気づき学びを広げていきます。そんなときの子どもたちは生き生きと目を輝かせて新しいことを発見し知識を積み重ねていく楽しさを体感するのです。
苦手なことや難しいことにも意欲を持ってチャレンジしようとする心、できなくても先生や友だちに励まされて頑張って克服していく態度、義務教育は人生の基礎を作る場です。
大人のみなさん、現在は厳しい競争社会に身を費やし勝ち抜くことが大事なことはわかります。
しかし、そんなみなさんも小学生の時のことを思い出してみてください。先生に怒られたこと、褒められたこと、友だちと遊んだことなどなど、どんなことが思い出されますか?
今社会で頑張れている基礎は、義務教育の時に先生から
「00ちゃんはやればできるじゃん。」「00ちゃんは絵がうまいね。いいとこあるね。」「すごいすごい、がんばったね。」
などと励まされ認められたから今があるのではないですか?
また、もしかしたら悪いことをした自分を泣いてしまうほど厳しく叱ってくれた経験かもしれません。
とにかく、義務教育は競争至上主義ではないことだけは確かです。
4 小学校国語Aの持つ意味
昨年の「全国学力・学習状況調査」で、小学校国語A問題が全国47位、最下位という結果に全県民が衝撃を受けました。しかしそれが、「静岡県の子どもの学力は全国最下位」というように過大解釈されたように思います。さらに「静岡県の学力は危機的状況。」「静岡県の授業は最低。」などという発言まで飛び出しました。
よく考えてみてください。義務教育9か年あるうちの、小学校6年生。そして国語Aと国語B、算数Aと算数Bがある中で、国語Aだけが最下位だったわけです。それが、「静岡県のすべての学力」のようになってしまいました。
同じ年に実施した中学校3年生は総合得点では全国6位です。これが評価されないで小学校の国語A最下位だけが大きく独り歩きしてしまいました。
それからというもの、新聞では「静岡県の学力」という特集が一年を通じて組まれ全県民が危機感をあおられました。使っている副教材が悪いからだという指摘も出ました。県議会本会議でも文教常任委員会でも質問の中心的話題になりつづけました。
しかし、またよく考えてみると、それほど県民こぞって県政こぞって問題視する重大な課題だっだのでしょうか?
静岡県の人口流出、北海道に続き全国ワースト2、企業立地数毎年減少などもっと重大な課題はあると思うのですが。
確かに騒いでくれたおかげで授業の見直しやテスト対策が進み、今年の結果は大幅に向上しました。
しかし、学校のことは学校を信用して任せてくれればなんとかします。
5 今後のありかた
全国学力調査の実施には60億円もの予算が使われています。日本全国、地域の学力を調査する目的のためなら、全校実施する必要はなく抽出方式で5%ほどのデータを採取すれば十分なはずです。
また、静岡県では国から結果が返ってくる前に、各学校で教師が採点をしておよその結果をつかんでいます。つまり、国ではベネッセなど外部委託して採点分析をし、県内すべての学校でも全員の分の解答用紙をコピーしてから採点し分析をするという二重の手間をかけているのです。結果を早くつかんで対応し指導するためということですが果たしてそれだけの費用対効果があるのか疑問です。
「私は、静岡の教育を受けて育った。」と県民が胸を張って語ることができるように、また教職員も「静岡の教育は真の教育だ。」と自信を持って教壇に立つようにしていかなければなりません。現に、全国の教育研究集会では、静岡県の実践発表は質が高い上に絶えず新しい取り組みを続けていることで高い評価を受けています。
全国テストの問題傾向が今の日本につけたい力であることは確かなので、授業改善に取り入れていくことは必要です。しかし、これまでに述べたように点数主義、競争主義に陥ることなく、目の前の子どもたちに「学ぶ力」をつけさせるという大事な目標に向かって心を一つにしていくことが何より大事です。
2013年09月11日
学力調査 川勝知事発言
学力調査 川勝知事発言について
「学力テスト全国最下位 子どもに責任はない。教師の責任だ。下位100校の校長名を公表する。」
とんでもない記事が飛び込んできました。
確かに、この衝撃的な結果をしっかり受け止め、指導する立場として責任ある対応がもとめられることは認めます。しかし、「校長名を公表する」ということは、校長個人の責任を問うことになり、ひいては学年の、担任の責任、個人の犯人探しということになりかねません。
義務教育とは、学区のすべての子どもが通う場であり、すべての子どもに等しく教育を受けさせることを基本としています。そして、テストは「平均点」で数値化されていることを理解していただきたい。
今、共生の教育、インクルージョンという理念が浸透しています。特別支援を要する子も普通学級を希望すれば普通学級で学習し、外国籍の子どもたちも日本語ができなくてもクラスの中で少しずつ学んでいます。担任が、手を掛け目を掛け日々育てています。もちろん、飛び級してもいいような優秀な子もいます。さまざまな子どもたち全員の「平均点」・・・
「平均点」を下げてしまう子たちが「犯人」になるようなことは絶対あってはなりません。
学力テストの結果は、教育の成果を測る一つの物差しであるといえます。小学校の平均点が毎年少しずつ下がっていること、中学生になると上位になることなど、原因をしっかり分析して手立てを講ずる必要があります。
「結果を公表しないのは教育界の隠ぺい体質だ。」という批判もよく聞きます。どの地域にも存在する義務教育の小中学校の学力テストの平均点を公表しその点数を論じ合うことが、地域にとって、子どもたちにとって有効なことかどうか・・
今回の調査で、静岡県の子どもが意欲と自信を持って学び続け「確かな力」を身に付けることができるよう、教職員の資質向上や教育環境整備に尽力していきたい。
「学力テスト全国最下位 子どもに責任はない。教師の責任だ。下位100校の校長名を公表する。」
とんでもない記事が飛び込んできました。
確かに、この衝撃的な結果をしっかり受け止め、指導する立場として責任ある対応がもとめられることは認めます。しかし、「校長名を公表する」ということは、校長個人の責任を問うことになり、ひいては学年の、担任の責任、個人の犯人探しということになりかねません。
義務教育とは、学区のすべての子どもが通う場であり、すべての子どもに等しく教育を受けさせることを基本としています。そして、テストは「平均点」で数値化されていることを理解していただきたい。
今、共生の教育、インクルージョンという理念が浸透しています。特別支援を要する子も普通学級を希望すれば普通学級で学習し、外国籍の子どもたちも日本語ができなくてもクラスの中で少しずつ学んでいます。担任が、手を掛け目を掛け日々育てています。もちろん、飛び級してもいいような優秀な子もいます。さまざまな子どもたち全員の「平均点」・・・
「平均点」を下げてしまう子たちが「犯人」になるようなことは絶対あってはなりません。
学力テストの結果は、教育の成果を測る一つの物差しであるといえます。小学校の平均点が毎年少しずつ下がっていること、中学生になると上位になることなど、原因をしっかり分析して手立てを講ずる必要があります。
「結果を公表しないのは教育界の隠ぺい体質だ。」という批判もよく聞きます。どの地域にも存在する義務教育の小中学校の学力テストの平均点を公表しその点数を論じ合うことが、地域にとって、子どもたちにとって有効なことかどうか・・
今回の調査で、静岡県の子どもが意欲と自信を持って学び続け「確かな力」を身に付けることができるよう、教職員の資質向上や教育環境整備に尽力していきたい。
2013年09月11日
学力調査について考える
静岡県全国学力・学習状況調査の結果について
2013年度の全国学力・学習状況調査の小学校6年国語で、静岡県の平均正答率が全国最下位という結果が出ました。教育関係者のみならず全県民にとって少なからずショックでした。「情けない、教育の在り方を見直せ。」「読書や新聞を読む習慣づけを」「短歌や俳句、美しい日本語をもっと学んで」などの声が新聞の投書に寄せられました。
6年生の国語の問題を見てみると、冊子になっていてめくること10数ページ、文字の量がぎっしりで20分ではとても読み通せないと感じました。普段行っているテストはA3一枚の一目で見渡せる問題を45分かけて回答するやり方です。全体の見通しができなくて、最後の4ページは未回答率が非常に高かったということでした。
また、「読み取ったことを40文字以上50文字以内で書きなさい。」という問題でつっかかりその先に進めないまま時間切れというパターンが多かったと聞きました。さらに、帯グラフから読み取れることを問う問題も意味が分からなかったということでした。
普段の授業では、確かに、限られた字数で意見をまとめたりすることはあまり指導していません。かえってたくさん書けた子がほめられているかもしれません。普段のテストも学習した教材の中から問題を出しているので、慣れている文章ばかりなのです。
このような反省から、漢字の読み書きはもちろん、短文づくり、文でまとめる、新しいことを読み取るなどのスキル学習に力を入れて次のテストに備える必要もあります。もちろん授業の中だけでなく、朝自習、モジュールなどを効果的に利用していけばいいと思います。
静岡県の授業研究は全国一進んでいるといっても過言ではありません。一人ひとりの学びを大切にして「学力」とは「学ぶ力」であるととらえています。問題を解決していく力、生きて働く力をつけるために日々授業改善に取り組んでいます。授業に対する姿勢を変える必要はありません。
静岡県の子どもたちも教職員も自信を失うことなく「学び」の本質を見つめていきましょう。
2013年度の全国学力・学習状況調査の小学校6年国語で、静岡県の平均正答率が全国最下位という結果が出ました。教育関係者のみならず全県民にとって少なからずショックでした。「情けない、教育の在り方を見直せ。」「読書や新聞を読む習慣づけを」「短歌や俳句、美しい日本語をもっと学んで」などの声が新聞の投書に寄せられました。
6年生の国語の問題を見てみると、冊子になっていてめくること10数ページ、文字の量がぎっしりで20分ではとても読み通せないと感じました。普段行っているテストはA3一枚の一目で見渡せる問題を45分かけて回答するやり方です。全体の見通しができなくて、最後の4ページは未回答率が非常に高かったということでした。
また、「読み取ったことを40文字以上50文字以内で書きなさい。」という問題でつっかかりその先に進めないまま時間切れというパターンが多かったと聞きました。さらに、帯グラフから読み取れることを問う問題も意味が分からなかったということでした。
普段の授業では、確かに、限られた字数で意見をまとめたりすることはあまり指導していません。かえってたくさん書けた子がほめられているかもしれません。普段のテストも学習した教材の中から問題を出しているので、慣れている文章ばかりなのです。
このような反省から、漢字の読み書きはもちろん、短文づくり、文でまとめる、新しいことを読み取るなどのスキル学習に力を入れて次のテストに備える必要もあります。もちろん授業の中だけでなく、朝自習、モジュールなどを効果的に利用していけばいいと思います。
静岡県の授業研究は全国一進んでいるといっても過言ではありません。一人ひとりの学びを大切にして「学力」とは「学ぶ力」であるととらえています。問題を解決していく力、生きて働く力をつけるために日々授業改善に取り組んでいます。授業に対する姿勢を変える必要はありません。
静岡県の子どもたちも教職員も自信を失うことなく「学び」の本質を見つめていきましょう。






